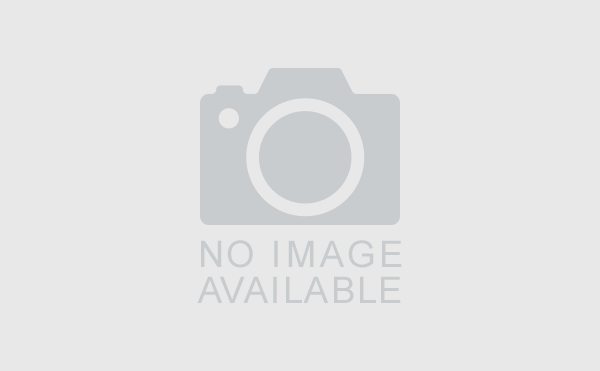シーバー病(踵骨骨端症)とは?成長期に多いかかとの痛み
シーバー病(踵骨骨端症)とは?成長期に多いかかとの痛み
お子さんが「かかとが痛い」と言って歩き方がおかしい、つま先立ちで歩くようになった…。
このような場合に考えられるのがシーバー病(踵骨骨端症)です。
主に小学生から中学生の成長期の男の子に多く見られる症状で、運動を頑張っている子どもほど発症しやすいのが特徴です。
💡シーバー病の原因
成長期のかかとの骨(踵骨)は、まだ完全に固まっておらず、「骨端線(成長軟骨)」と呼ばれる柔らかい部分があります。
この部分にアキレス腱や足底の筋肉が強く引っ張る力が繰り返しかかると、炎症や微細な損傷が起こり、痛みが出ます。
特に以下のような条件が重なると発症リスクが高くなります:
- ジャンプやダッシュが多いスポーツ(サッカー、バスケットボール、陸上など)
- 成長期による骨と筋肉のアンバランス
- 硬いグラウンドや靴のクッション性不足
- 偏平足や足首の柔軟性不足
成長に伴い骨が急激に伸びる一方で、筋肉や腱がそれに追いつかないため、アキレス腱や足底筋膜がかかとの骨を引っ張り、炎症が起こりやすくなるのです。
⚠️症状の特徴
- かかとを押すと痛い
- 運動中や運動後にかかとがズキズキ痛む
- 朝の一歩目が特に痛い
- かかとを浮かせてつま先で歩くようになる
- 両足よりも片足に出ることが多い
放っておくと、痛みを避けるためにつま先歩きや偏った体重のかけ方が習慣化し、膝・腰・姿勢のバランスまで崩す二次的不調につながることもあります。
🏥毛馬やまぐち整骨院でのアプローチ
当院では、シーバー病を単なる「かかとの痛み」として捉えるのではなく、全身のバランスと動きの中で原因を探ることを重視します。
今まで膝や足の痛みで来院された患者様の中でも、実際にはかかとや足底へのストレスが原因だったケースは非常に多く見られます。
- 足首やふくらはぎの筋緊張の緩和: マッサージやストレッチでアキレス腱の引っ張りを軽減
- 足裏・骨格バランスの矯正: 骨格や足のアーチを整え、衝撃の分散を促す
- 神経の促通性を高める施術: 筋肉の働きを正しく引き出し、再発しにくい状態へ導く
また、必要に応じてテーピングやインソールでサポートし、日常生活でも痛みが出にくい環境を整えます。
痛みが落ち着いてからは、再発予防のための体の使い方・姿勢指導を行うことも重要です。
🏃♂️セルフケアと予防法
- 運動後はふくらはぎとアキレス腱をしっかりストレッチ
- クッション性の高い靴を選ぶ
- 痛みが出たときは無理せず休む
- お風呂で温めて血流を促進し、筋肉の柔軟性を保つ
- 偏平足や外反母趾など、足の形にも注意する
特に成長期のお子さんは、身体の変化が早く、少しの負担でも痛みが出やすい時期です。
早めに整骨院で原因を見極め、成長を妨げない正しいケアを行うことが大切です。
❓よくある質問(Q&A)
Q1. シーバー病は自然に治りますか?
成長期が終わると骨が固まり、自然に痛みが軽減することもあります。
ただし、痛みを我慢して動き続けると炎症が長引き、治りが遅くなるため注意が必要です。
痛みが強い時期は安静をとり、整骨院でのケアを受けることをおすすめします。
Q2. 運動はいつ再開できますか?
痛みが完全に取れてから少しずつ再開するのが理想です。
整骨院では、痛みの状態を確認しながら運動復帰のタイミングを一緒に判断します。
再発を防ぐために、復帰前には柔軟性や姿勢のチェックも行います。
Q3. シーバー病を予防するにはどうすればいいですか?
練習後のストレッチや、クッション性のあるシューズ選びが重要です。
また、偏平足や姿勢の崩れがある場合は、早めに整骨院で調整を行うことで予防につながります。
Q4. テーピングやインソールは効果がありますか?
はい。テーピングやインソールは、かかとへの衝撃を分散させるため非常に有効です。
一人ひとりの足の形や動き方に合わせて使うことで、痛みの軽減と再発防止が期待できます。
🌿まとめ
シーバー病は、成長期特有の一時的な症状であることが多いですが、放っておくと慢性化や二次的不調を招く恐れがあります。
整骨院での適切な施術と、家庭でのストレッチやケアを継続することで、多くの場合は痛みの軽減・再発防止が可能です。
最終的な目標は、身体の使い方を改善し、負担を軽減させることで生活や競技への早期復帰です。
痛みを我慢せず、早めのケアで元気にスポーツを楽しめる身体づくりを目指しましょう。
#姿勢矯正#骨盤矯正#猫背矯正#友渕町#大東町#毛馬町#都島区#大阪市整骨院#整体
#肩こり#腰痛#ストレートネック#頭痛#交通事故#ムチウチ#膝痛#ギックリ腰#捻挫#自律神経